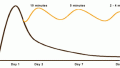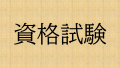まとめ、感想
まとめ
- 本を最良の教師とするためには、読み手の積極性と技量が重要である。
- 読書には、「初級読書」「点検読書」「分析読書」「シントピカル読書」の4つのレベルがある。
- 本の内容そのままではなく、自分の言葉で理解することが「真の理解」や「新たな発見」につながる。
- 文学においては、その世界を自分自身の体験とすることだと著者は述べている。
感想
- 現代では、本だけでなくネットも有力な情報源になってきている。
- その一方で、ビジネスや技術に関する情報が氾濫しており、本書に書かれている考え方や手法が有効である。
例)読む価値があるかの判断、著者のバックグラウンドを理解しつつ自分の言葉に変換 等 - 昔は著者や主題に関する研究者・有識者たちと対話することが難しかった。メールやSNSなどコミュニケーション手段が高度化した現代においては、新しい手法があり得るのではないか。
「本を読む本」について
| 表紙画像 | 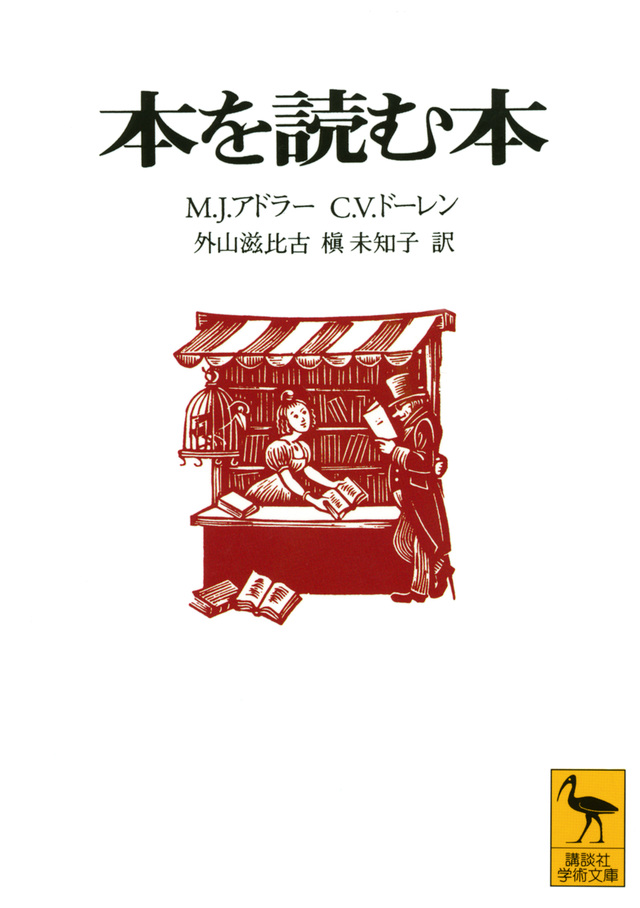 |
| 書籍名 | 本を読む本 (講談社学術文庫) |
| 著者 | M・J・アドラー C・V・ドーレン 外山滋比古(訳) 槇未知子(訳) |
| 出版社 | 講談社 |
| 出版日 | 1997年10月9日 |
なぜ本の読み方が重要なのか
読むという行為には、積極性が欠かせない。そして積極的な読み方であればあるほど、それは良い読み方である。読む行為を受け身の行為ととらえる人は多い。しかし、情報をしっかりと受け取るには技術が必要なのである。書き手の意図をどれだけ理解できるかは、読み手の積極性と技量にかかっている。
教育学においては、「教えられて」学ぶことと、「発見して」学ぶことを区別して考える。この違いは主に何から学ぶかにある。「教わる」場合には、本を読む、あるいは話し手から学ぶ。一方で、「発見する」場合には、学習者が自分で自然や外界に働きかける。
しかし、「発見する」ことが能動的であり、「教わる」ことが受動的であると考えるのは誤りである。「教わる」際にも、頭を使って考える必要がある。読書技術には、観察力、記憶力、想像力、思考力など、「発見する」場合に必要なすべての力が要求される。理解を深めるための積極的な読書は、本質的に手助けのない「発見」と変わらないからである。
教師から「教わる」場合には、教師が目の前にいれば質問もでき、さらなる説明を聞くこともできる。だが、読書の場合は読み手自身が問いに答えなければならない。学生時代は教師に頼ることもできるが、学校を出てから教養を身につけるには読書しかない。だからこそ、生涯学び続け「発見」し続けるためには、本を最良の教師にする方法が必要なのである。
読書のレベル(4つのレベル)
初級読書
初級読書は、個々の言葉を識別し、その文が何を述べているのかを理解する読書。
点検読書
点検読書は、短時間で本の全体像をつかむための読書。
次の2段階の読み方をし、本の構成や主な論点に加えて全体を把握する。
- 読もうとしている本が時間を割いて読む価値のある本なのかを品定めを行う。
- まず、じっくり読む価値のある本か否かの判断するために以下を行う。
- 推測表題や序文から、本の取り扱う内容や分野を把握・推測
- 目次から、本の構造を把握・推測
- 索引から、キーワードを把握・推測
- カバーにあるうたい文句から、論点を把握・推測
- じっくり読む価値のありそうと判断した場合は以下を行う。
- 重要そうな章をよく読む(特に冒頭と章末)
- ところどころ拾い読みする
- まず、じっくり読む価値のある本か否かの判断するために以下を行う。
- 1によって読もうとしている本の構成や主な論点が頭に入れた上で、通読することだけを念頭に置き、途中で気になるところがあっても一旦は脇に避けておき、表面的に読む。
分析読書
分析読書は、対象となる本を徹底的に読み込み、自分の血肉とするための読書。
分析読書では、規則に従って三段階に分けて読書を進める。
- 第一段階 概略をつかむ
- 第二段階 内容を解釈する
- 第三段階 本の内容を批評する(またそれを通して著者と対話する)
分析読書の規則(=ルール) 第一段階 概略をつかむ
- 第一の規則
今読んでいる本は分類上、何に関する本かを知ること。 - 第二の規則
本のプロット、本筋を2-3行でまとめられるようにすること。 - 第三の規則
全体がどのような部分から構成され、どのように配置されているか示せるようにすること。 - 第四の規則
著者がどのような問題から本を書いたのか知ること。
分析読書の規則(=ルール) 第二段階 内容を解釈する
- 第一の規則
読者が著者と折り合いをつけること(=著者の言葉の使い方を理解すること)。 - 第二の規則
命題を見つけること。 - 第三の規則
論証を述べているパラグラフを見つける、または論証を構成する命題が含まれている一連の文を集めて論証を組み立てること。 - 第四の規則
著者の解決が何であるか検討すること(= 著者が解決しようとした問題のうち、何が解決し何が未解決に終わったか)。
分析読書の規則(=ルール) 第三段階 批評
- 第一の規則
まずは「この本がわかった」とある程度確実に言えること。そうした上で、賛成/反対/判断保留の態度を明らかにすること。 - 第二の規則
反論はけんか腰にならず、筋道を立てて行うこと。 - 第三の規則
反論は解消できるものだと考えること。
シントピカル読書
シントピカル読書は、同一主題について複数の本を読んでいく並行的な読書。
進め方の例を次に示す。
- 最初に追求する主題を決める。
- 主題を決めたら、図書館の目録、人からのアドバイス、書籍の文献一覧表などを元に文献リストを作成する。
- 集めた文献を点検読書し、それぞれの文献から自分の要求に最も密接に関連した箇所を見つけ出す。
- 追求する主題に関連する箇所の拾い出しが終わったら、どの文献にも依存しない読み手自身の言葉で全ての書籍を理解する。
- ここまでの作業を踏まえ、主題の中で最も知りたい内容を知るための一連の質問を立てる。
- 質問を立てたら各文献の主張を整理し、論点を明確にする。
- 明確にした質問と論点に対して、論考を分析し、質問を解決しようと試みる。
おまけ 名言集
文学を本当によく読むためには、ただ、その世界を経験することしかない。
講談社「本を読む本」215ページより
二流の本は、再読したとき、奇妙に色あせてみえるものである。もっとすぐれた本の場合は、再開したとき、本もまた読者とともに成長したようにみえるものだ。
講談社「本を読む本」251ページより